特別インタビュー②
芸能を未来に繋ぐために―照屋林賢に聞く(後篇)
概要
90年代以降、沖縄の音楽文化・芸能は広く親しまれるようになったが、そのきっかけのひとつとなったのが、りんけんバンドのメジャーデビューとそれ以降のブレイクだった。地域の風習や伝統を織り込みながら、沖縄発のポップサウンドを打ち出した彼らのスタンスは、同時代に世界各国で盛り上がりを見せたワールドミュージックの潮流とも共振するものであった。
中心人物である照屋林賢は、琉球古典音楽家の林山を祖父に、戦後の沖縄芸能の流れを作り出した林助を父に持つという沖縄芸能のサラブレッド。このコロナ禍では自身が経営する北谷のライヴハウス「カラハーイ」からいち早く番組配信を開始し、現在まで毎日のように生配信を続けるなど、沖縄音楽の未来を常に見据えてきた
「伝統」に対するしなやかな思考も持つ照屋林賢は、地域芸能の今後についてどのように考えているのだろうか。「地域芸能と歩む」プロジェクトの2020年度報告書のため、2回に渡って行われたリモート・インタビューのロングヴァージョン(後篇)をお届けしよう。
(インタビュー・文/大石始)
芸能を未来に繋ぐために――照屋林賢に聞く(後篇)
前篇はこちらから。
●「沖縄のリズム」の創造――シーケンサーの導入
――「沖縄のリズム」を作るうえで、芸能や民謡の伝統をどのように取り入れようと考えていたのでしょうか。
照屋林賢:たとえ伝統芸能であろうとも「これが伝統だからそのまま受け継いでいけばいい」というわけではないと思っているんですよ。中国やベトナムに行くと、沖縄に渡った文化の源流があるわけですよね。三線ひとつとっても、似た楽器がアジア中にある。つまり、どこかから持ってきた伝統楽器に誰かが新たな改良を加え、自分たちの楽器を作ってきたわけですよね。音楽もそうやって発展を繰り返してきたわけだし、僕らもその発展の中にいると思うんです。
リズムに関して言うと、新しいリズムを作るにあたってふさわしいドラマーがなかなかいなくて苦労しました。そんなときに出会ったのが(音楽データの自動演奏機能を持つ機器である)シーケンサーでした。シーケンサーはこちらの言うことを聞いてくれるし、言った通りにやってくれる。僕にとっては力強い仲間ができたという感覚だったんですよ。
――1987年にマルテルからカセットテープで発売されたりんけんバンドのファースト・アルバム『ありがとう』では、シーケンサーとシンセサイザーが多用されています。林賢さん自身素晴らしい三線奏者であるにもかかわらず、三線のフレーズもシーケンスに置き換えられていますね。『ありがとう』というアルバムでは、それが独特の質感を生み出しています。
照屋林賢:名人と呼ばれる人たちの三線のフレーズって、「こう弾くと昔の味が出てくる」という一定のルールみたいなものがあるんです。それを外すと少し素人っぽく聞こえてしまう。それは登川誠仁さんのような名人の演奏を分析してわかったことでもあるんです。(アルバムの表題曲である)「ありがとう」で使っているフレーズは、沖縄音楽の基本的な音の動きを意識して作ったものでした。
音楽的に言えば、三線のフレーズは単純にドレミファソラシドに置き換えられない部分があるんです。音の揺れというかね。たとえば、ほんの少しだけフラットに弾くことによって「らしく」なる音というものがあるんですね。半音よりももっとわずかな音の上げ下げなんですが、それをやることによって、ぐっと悲しく聞こえてくる。シーケンサーはそうした微妙な音を表現できないんですが、逆にパキッとした明るさが出ることもあります。「ありがとう」はまさにそうした効果が出た曲じゃないかと思います。
――林賢さんのご著書『なんくるぐらし』(筑摩書房)では、シーケンサーの導入についてこう書かれています。「本物の三線を弾かずに、シークエンサーやシンセサイザーといった機械を使って、ポコポコと音を出したら面白いんじゃないか。あまりうねらない、カチッと乾いたリズムでやったら気持ちいいんじゃないか、と思った」と。うねるリズムというのは、すなわちグルーヴのことですよね。音楽の魅力そのものでもあるわけですが、りんけんバンドはその魅力をみずから捨て去ることで、新たな沖縄のリズムを生み出そうとした。その試みは非常に現代的ですし、先駆的なものだったとも言えます。
照屋林賢:通常の芸能や沖縄音楽の発想とは逆ですよね。沖縄の音楽は三線のテクニックによって感情を表すところがあるんですが、歌も感情たっぷりで三線も感情たっぷりだと、沖縄以外の人たちにはちょっと馴染みにくいんじゃないかと思ったんですよ。リズムは少しクールに聞こえるかもしれないけれど、その中に情のある歌が乗ってくる。そういうバランスによって作り出せるものがあるんじゃないかと考えていたんです。
沖縄の音楽にも今までとは違う魅力を与えなくちゃいけないんじゃないかと思っていましたし、「必ずこうじゃなきゃいけない」という発想に縛られないことが大事なんですよね。沖縄にも頑固なオヤジは多いんですよ(笑)。これ以上他の世界には行けないだろうなというミュージシャンもいっぱい見てきましたけど、りんけんバンドは違う。地球上に新たな音楽を生み出すために貢献したいし、そのことを楽しみたいと思ってバンドを続けてきたんです。
――『なんくるぐらし』ではこんなことも書かれています。「ドラムは洋楽のロックビートがいい。だが、ロック的なスタイルでも沖縄のリズム感でたたける人がほしいと、僕はいつも思っていた」と。たとえさまざまなスタイルに取り組もうとも、根底にあるのは「沖縄のリズム感」であるということですよね。ただ単にロックと沖縄民謡や芸能を繋ぎ合わせるのではなく、どのように有機的に結びつけるか。
照屋林賢:沖縄音楽の要素をふりかければ、それで新しいものが生まれると考えている人はたくさんいると思うんですよ。そういうことではなくて、もっと音楽の核の部分、マグマの部分まで考えたほうがいいんじゃないかと考えていました。
沖縄の音楽をただ単にスパイスとして残すのではなくて、「ロックのリズムでも沖縄の人がやるとこうなるんだ」という力強さと発想力が必要だと思うんですよ。そうした感覚が生まれたとき、長い沖縄音楽の歴史に新たな1ページが加わると思うんですよね。
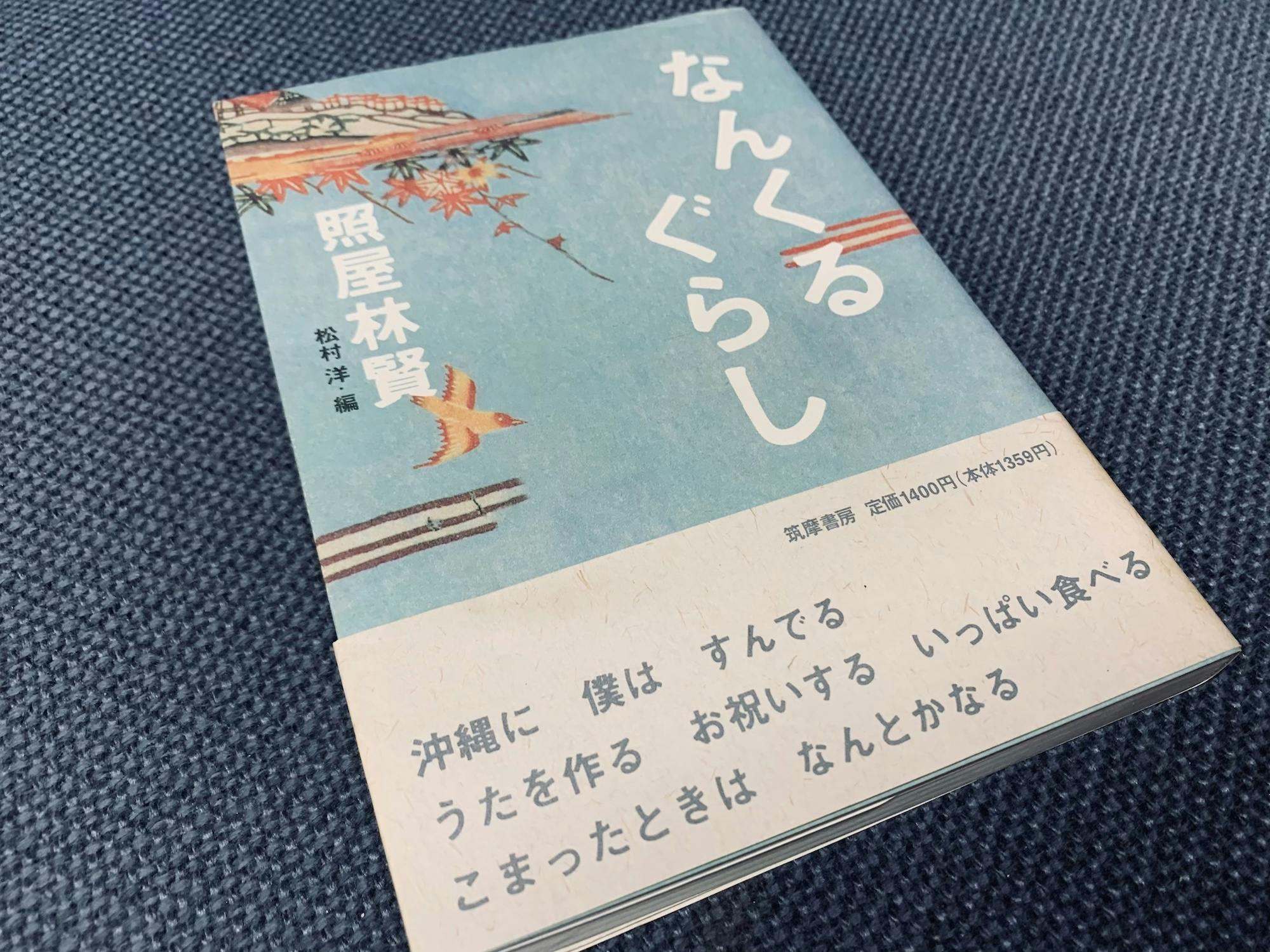 照屋林賢・松村洋著『なんくるぐらし』
照屋林賢・松村洋著『なんくるぐらし』
●本土とアメリカばかりを向いた地元をどう変えていくか
――『なんくるぐらし』には、りんけんバンドの結成当初のことも書かれています。「自分が立っている地点から半径100メートル、50メートル、いや3メートルでもいい。その範囲にいる人たちに楽しんでもらえればいいと考えた。隣のおばさんが喜んでくれればいい。これがりんけんバンドの基本的な考え方だった」と。結成当初のりんけんバンドは内地ではなく、あくまでも地元を意識していたのでしょうか。
照屋林賢:地元の人たちと一緒に楽しめるということが大事だったんです。周りの人たちに盛り上げられてヤマハのコンテストに出たりもしましたけど、やっぱり80年代前半の段階では本土で受け入れられなかった。『ありがとう』ができたときも、母親や兄弟、友達とか一番近い人たちにまず聞いてもらったんですよ。東京のレコード会社のディレクターではなくてね。「おもしろいね、いい曲だね」と言ってもらえたとき、すごく嬉しかった。80年代前半はなかなか厳しい時代でしたけど、「こういうことを続けていれば、きっといつかは誰かが見つけてくれるはずだ」と思っていました。
1985年には(沖縄市営球場で開催された)ピースフルラブ・ロックフェスティバルにも出演しましたが、自分たちでも場違いだと思っていました。当時、三線が入ったバンド編成は珍しかったし、僕らみたいなバンドいなかったんですよ。「帰れコール」を浴びましたから。
――当時の沖縄は今以上にアメリカ志向のバンドが多かったんでしょうか。
照屋林賢:多かったですね。地元の音楽に魅力を感じない人たちばかりだった。当時はレコード屋さんに行っても沖縄の音楽のレコードは店頭には置いてなかったんですよ。照屋楽器店もそう。民謡のレコードも普段は倉庫に置いてあって、欲しい人はリストを見て店員に持ってきてもらうんです。ショーウインドウには民謡のレコードは置いてなかった。そういう時代ですからね。
本土からやってくる音楽にみんな気持ちが向かっていて、沖縄も六本木あたりとあまり変わらなかった。音楽からファッションから、80年代はすべてがそういう感じでしたよ。
――林賢さんの中にはそうした地元の状況を変えたいというモチベーションもあったんですか。
照屋林賢:多少はあったかもしれないですね。当時は入場無料のコンサートで演奏していても、舞台の目の前をみんな素通りしていくんですよ。BGMのような感覚というか。一生懸命やっていてもなかなか伝わらない。腐ってしまいそうな時期もありましたよ。
――そうした状況が変わり始めたのはいつごろからですか。
照屋林賢:石川まつりというイヴェントにりんけんバンドも出たことがあったんですよ。(りんけんバンドの看板シンガーである)上原知子が入団して間もないころだったんですけど、彼女から「民族衣装を着てくれ」と言われたんですね。「そうじゃなかったら入らない」と。揃いの衣装でステージに上がったら、それまでとお客さんの反応が全然違ったんです。
上原知子が入ったことも大きかったと思いますけど、揃いの衣装でやるようになったのは大きかった。そのすぐ後、関係者向けのライヴをやったんですけど、その時の反響もすごかったんですよね。「沖縄の芸能をこんな風に進化したバンドは今までなかった」と沖縄の関係者から言われましたし、そのときに「これはいけるな」と思いました。
 りんけんオリジナル三線と3種類のチェレン
りんけんオリジナル三線と3種類のチェレン
●「言葉を変えられるのは、舌を抜かれるのと一緒」
――ファースト・アルバムはその後、1990年にWAVEから全国版としてリリースされました。
照屋林賢:そのころ複数のレコード会社から話があったんです。でも、いつも条件で引っかかる。『ありがとう』を出すにあたって、新しくレコーディングをし直そうと言うんですよ。しかも歌詞を標準語に直して撮り直そうと。その話を聞いてすぐに「だったらやめましょう」と断りました。WAVEはそのままでいいということだったので、だったらここから出そうと話がまとまりました。
りんけんバンドの音には生命が宿っているんです。たとえメジャーのレコード会社でも、言葉を変えることはできない。昔、とある先輩に言われたことがあったんですよ。「曲は自分の子供だと思いなさい」と。今でもそういう気持ちでやっています。言葉を変えられるのは、舌を抜かれるのと一緒ですから。
――80年代から90年代にかけてはワールドミュージックのブームが起きましたよね。世界中で伝統音楽や民族音楽をアップデートしようというアーティストが登場しましたが、そうした動きからは刺激を受けましたか。
照屋林賢:受けましたね。すごくワクワクしていましたし、素晴らしい時代だったと思います。最初に一緒にやったのは3ムスタファズ3(註:りんけんバンドの91年作『リッカ』には同バンドのメンバーが参加している)。変なやつらでしたけど、とても刺激になりました。
それまでりんけんバンドはとても孤独だったんですよ。だけど、海外に行ったら同じような考え方の人たちがたくさんいた。世界中でいろんな人たちと会いましたし、とても心強かったですね。
――90年代にはエレクトリック三線であるチェレンを開発し、その名も『チェレン』(95年)というアルバムもリリースしました。
照屋林賢:三線は楽器の構造としてはとても原始的なんですよね。もちろんその魅力もあるんだけど、三線も進化したっていいんじゃないかと思っていたんです。照屋林助は電気三線や電気四線みたいな変わった楽器を作っていましたけど、それをさらに発展させたもの作れないかと。三線に変わる沖縄音楽の基本を作りたかったんです。
 2018年に誕生した3号機のチェレン
2018年に誕生した3号機のチェレン
――そろそろ最後の質問です。沖縄の音楽や芸能を次の世代に繋いでいくために、林賢さんは何が必要だと思われますか。
照屋林賢:沖縄の民謡の世界では「古いものはいいものだ」というベーシックな考え方があって、それだけだとなかなか前に進めない。伝統を守ることは大事だけど、守っているだけではみんな同じ歌い方になってしまう。それは音楽の発展とはまた別の話だと思いますね。かといって他のジャンルの人とやっただけだと、単なる商品作りで終わってしまう。
僕は今後、セルフマネージメントを提唱していこうと思っているんですよ。自分の思い通りに、好きなように音楽を作ったらどうかと。機材も安くなってますし、自分で発信するのも簡単になった。そこに希望を持っているんです。
あと、「区長アプリ」というものを作りたいとも思っているんですよ。地域の情報を区長さんにアップしてもらって、それをアプリを通してまとめていくという。例えば「●●家の長男は歌がとても上手いらしい」とか(笑)。そういう情報をもとに地域の芸能を繋げていって、例えば沖縄市のミュージックタウンみたいな場所で芸能の教育を行う。そういうことも可能だと思うんです。
――なるほど、おもしろいですね。
照屋林賢:ミュージックタウンも教育の現場として活用するべきだと思っているんです。あそこができてから11年ぐらい経ちますけど、11年ということは開館当時10歳だった子供が20歳を超えているわけですよね。それだけの時間があれば、教育を通していろんなことができたはず。5年10年と時間をかければ、芸能に関わるさまざまな人材を育てることができるはずなんです。
そうした人材をどのように育てていくか、すごく重要な問題だと思います。僕から見ると、沖縄はまだまだ優秀な人材が育っていない。芸能をやる人間だけでなくて、それをサポートする人たち、例えばエンジニアやマネージメントのノウハウがある人材を育てる必要もありますよね。いくら芸能に優れた若い世代を育てても、一本釣りで他のところに持っていかれてしまうんですよ。
自分が信じてきたことはそれぞれにあると思うんです。それをそれぞれがやったらいいと思うし、僕も自分が信じていることを続けていきたい。コロナが来ようとも変わらない価値観はみんな持っていますからね。自分たちが納得するものを、できるだけ丁寧にやっていく。ただの商品作りはやめよう。それが今の僕の気持ちですね。
(了)